【書評】『1440分の使い方』は時間の使い方を優れた構成で教えてくれる本
『1440分の使い方 ──成功者たちの時間管理15の秘訣』は日々が忙しいという人に向けて、時間の使い方を教えてくれる本です。
世に出回っている数ある時間管理術の全体像を知るのに最適な本だといえます。
また、タイトルにあるように、本書は成功者たちにインタビューを行い、その共通項から成功法則を見出すというアプローチのもの。
『思考は現実化する』や『7つの習慣』もこうしたアプローチをとっています。
こうした本は、すべてにおいて科学的根拠があるわけではありません。しかし、一人の成功者の持論や経験をまとめたものよりは参考になるかと。
本書は成功者たちの発言を紹介しつつ、研究内容を引用している部分も見受けられます。
1440分の使い方で紹介されるユニークな方法論
ToDoリストはつくるな
本書ではやることをまとめたリスト・ToDoリストは作成するなと主張しています。
ToDoリストは期日が書いてあっても、「この時間にやる」という予定を書かないため、いつまでたっても手をつけられなかったり、未完了のまま放置してしまうことが多いからです。
そこで、ToDoリストではなく、スケジュール表を使い、そこにやるべきことを入れていくべきだといいます。
これによって、タスクの管理はこれまで通り行うことができ、ToDoリストのデメリットを解消することができるのです。
タスク管理の定番ツールであるToDoリストを否定するというのは非常に面白い。
仕事が終わってなくても、「予定」が終わっていればストレスは軽減される
金曜日に仕事を残して退勤すると、仕事を残していることを思い、憂鬱になる人が多いのではないでしょうか。
これを解決する簡単な方法を本書は提示しています。
タスクはToDoリストではなくスケジュール表に入れる。なんと、たったこれだけのことで心が解き放たれ、ストレスが減り、認知能力が高まる。フロリダ州立大学の研究によれば、ツァイガルニク効果(未完了のタスクによって意識的・無意識的に悩まされる現象)は、タスクを達成するための 予定を立てる だけで克服できるという。
ケビン・クルーズ(2017)『1440分の使い方 ──成功者たちの時間管理15の秘訣』パンローリング株式会社 (Kindleの位置No.375-)
パソコンでなくノートでメモを取れ
ぼくは根っからのパソコン党ですが、本書はノートを使うべきと主張します。
最初の実験では、生徒たちにTEDのスピーチを見せてノートを取らせ、30分後それに関するテストを実施した。すると、事実を問う質問に関しては、ノートパソコンを使った学生も手書きの学生も同じ点数だったが、コンセプトを問う質問に関してはパソコン使用者のほうが点数が悪かった。
ケビン・クルーズ(2017)『1440分の使い方 ──成功者たちの時間管理15の秘訣』パンローリング株式会社 (Kindleの位置No.765-)
「だったら、パソコンでメモを取るときの弱点を認識したうえで、パソコンを使えばいいじゃないか」。
上記のように考えましたが、これもダメな様子。
パソコンを使った学生は、鍵となるコンセプトをメモするのではなく、スピーチをそっくりそのまま書き取っていた。その点に気づいた博士たちは、第二の実験で、自分の言葉でノートを取るよう、パソコン使用者に具体的に指示した。しかし結果は同じだった。手書きの学生のほうがメモの内容をよく思い出せたのである。
ケビン・クルーズ(2017)『1440分の使い方 ──成功者たちの時間管理15の秘訣』パンローリング株式会社 (Kindleの位置No.986-)
ポモドーロ・テクニックを使え
ポモドーロ・テクニックは、よく紹介されることがあるため、知っている方も多いでしょう。
25分働いたら、5分休むといった形で、作業と休息を比較的細かい単位で繰り返すことで、生産性の向上を目指す手法です。
本書でも、インタビューや研究内容をもとに、ポモドーロ・テクニックが紹介されています。
人間は本来90分間隔で、集中力とエネルギーがともに最大の状態から、生理学的な疲労状態へ移行する。(中略)そこで、終日90分間隔で水を飲む、歩く、健康的な軽食を食べるといった短い休憩を意識的に取るようシュワルツは提案している。
ケビン・クルーズ(2017)『1440分の使い方 ──成功者たちの時間管理15の秘訣』パンローリング株式会社 (Kindleの位置No.1840-)
やることよりもやらないことを明確にする
なにかをやるためには「やめること」を決めるほうが大切です。
組織の方針を説明したり目標達成のための行動を定めるときに、やめることを明確にすると、やることを決めるよりも具体的にやるべきことが見えてくるとぼくは考えています。
例えば、企業の経営方針で「上場を目指す」「ハードワークを推奨する」よりも「上場は絶対にしない」「残業は絶対にしない」のほうが、企業の行動が具体的に見えるわけです。
『1440分の使い方』の読むべきポイント
- 15以上ある時間の使い方・作り方に関する方法論(章が細かく分けられて、内容は具体的であるため、読みやすい)
- 成功者へのインタビューの内容や紹介されている研究の内容
本書を読んでいて感じたのは、章が細かく分かれていること。多くの場合、それぞれの章で言いたいことが明確であるため、すんなりと頭に入ってきます。
科学的根拠に基づいて、より正確な時間管理をするのならば、さらに探求する必要があるでしょう。
しかし、世に出回っている数ある時間管理術の全体像を知るのに最適な本だといえます。
Kindle版は非常にリーズナブルなので、気になる方はぜひ。
ネガティブな人がポジティブ思考になるには。事実と思い込みを切り離す練習から始めよう。
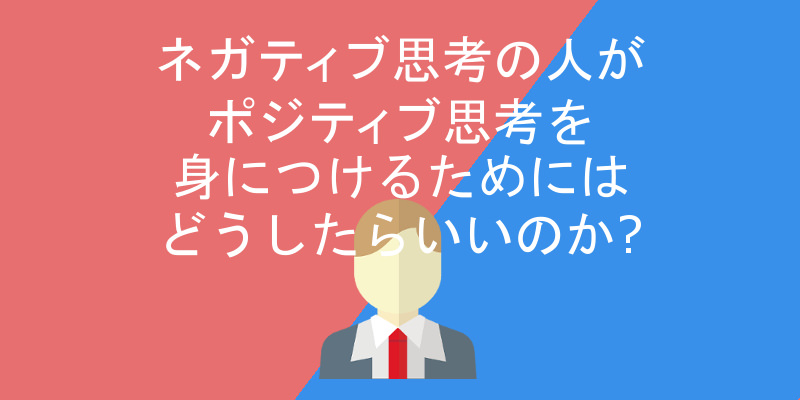
「ポジティブ思考のほうがよい」というものの、ポジティブ思考について論理的に説明できる人は少ないのではないでしょうか。
ポジティブ思考・ネガティブ思考は、説明スタイルによって説明できると過去に説明しました。
また、ポジティブ思考・ネガティブ思考の利点について説明したうえで、その思考は変えられると下記で書いています。
関連記事 知ると考え方が変わる。ポジティブ思考のメリットとデメリットはなにか。ネガティブ思考にもメリットはあるのか。
ここでは、ネガティブ思考の人がポジティブ思考になるにはどうすればよいのか具体的に説明していきます。
- 1.事実と感情を切り離す
- 2.ストレス解消法という観点でも同じことが述べられている
- 3.事実と感情を切り離す練習の実践例
- 4.ネガティブ思考の人がポジティブ思考になるには「事実と感情」を切り分けて、無根拠な感情に反論しよう
1.事実と感情を切り離す
ポジティブ思考になるためには、起きた事実とそれに対して思い込みを切り離す訓練が重要です。
私たちは何かが起こると、無意識に物事を解釈してしまいます。
そこで、一歩立ち止まって「自分はこう考えているのか」と考えることで、物事の解釈をポジティブな方へ修正していくことができるようになります。
私たちは困った状況(Adversity)に直面すると、それについて考えをめぐらす。考えはすぐに思い込み(Belief)となって固まる。この思い込みはあまりに習慣的になっていて自分では気づかないことも多い。
マーティン・セリグマン(1991)『オプティミストはなぜ成功するか』パンローリング株式会社 (Kindle の位置No.3578-)
1.1.説明スタイルを知る
先程も紹介した記事で書いたように、ポジティブ思考であるかネガティブ思考であるかというのは、物事の解釈である「説明スタイル」によって決まります。
例えば、ミスをして怒られてしまったときに、「自分はダメな人間で、一生この状態のままである」と考えるのと、「今回は注意不足だった。次は気をつけよう」と解釈するのとでは、大きく思考が異なることがわかるでしょう。
ポジティブ思考とネガティブ思考は、曖昧な認識で語られることが多い。
そこで、まずポジティブ思考とは物事の解釈のことを指すと認識してください。
1.2.事実と思い込みと結果がある
この本ではずっと、どういう思い込みがあきらめを生むかを示してきた。これからはどうしたらこの悪循環が断ち切れるかを学ぶ。最初のステップは、困った状況と思い込みと結果の因果関係を知ることだ。第二のステップは自分の日常生活で、これらA(困った状況) B(思い込み)C(結果)がどのような作用をしているかを知ることだ。これらの方法は、二人の世界的認知療法セラピスト――バンダービルト大学心理学教授スティーブ・ホロン博士とニュージャージー州立医科歯科大精神科教授アーサー・フリーマン博士――と私が協力して開発した、正常な人々のための説明スタイル改革講座の一部である。
マーティン・セリグマン(1991)『オプティミストはなぜ成功するか』パンローリング株式会社 (Kindle の位置No.3578-)
下記のような言葉が出てきました。
- A:困った状況(実際に起こった客観的な事実。本記事では事実と書きます)
- B:思い込み(困った状況をどう解釈するか。感情は結果にする、感情は思い込みかどうか測定できないから)
- C:結果(自分の行動や感情)
ペンシルバニア大学のセリグマン教授は本書のなかで、日常の出来事についても、このABCを書いてみることを推奨しています。
これがまさに、事実と思い込みを切り離す練習であるとぼくは考えています。
普段の生活のなかでは、このようなことを頭の中で考えてはいません。
しかし、これを意識的に行うことによって、自分の思考を認知し、いずれはコントロールできるようになります。
1.3.何かが起きたら、事実と思い込みと結果に分けて、さらに反論してみる
1.3.1 事実と思い込みと結果に分ける
上記の思考と合わせて、自分の感情に反論してみることは、ポジティブ思考になるのに効果的です。 例えば下記のようなことがあったとします。
- 些細なミスで上司に迷惑をかけてしまった。上司は怒らなかったが私に失望したはずだ。私はショックだった。
まずこれをシンプルに、事実と感情に分けてみましょう。
- 事実:些細なミスをした。上司に迷惑をかけてしまった。上司は怒らなかった。
- 思い込み:上司は私に失望した。
- 結果:私はショックだった。
こう考えると、上司が私に失望したことは事実かどうかはわからないと気付けます。
また、「私はショックだった」理由が、上司に失望されたことであるのなら、事実がどうかわからないものにショックを受けても仕方のないことだとわかります。
1.3.2 反論してみる
このようにして反論を考えてみましょう。
- 反論:些細なミスだし、上司は怒らなかったのだから、失望されたかはわからない。わからないことにショックを受けても仕方がない。
ぼく自身もなにかをやってしまったときには、いつも物事をネガティブに受け取り、ショックを受けますし、ストレスも感じます。
しかし、少し冷静になって、事実と思い込みを切り分け、それに対して反論をしてみると、「気にしても仕方のないことを気にしている」ことに気づくことができます。
これがポジティブ思考を身につけるための第一歩です。
物事を受け取った瞬間はネガティブな解釈をしますが、意識的に考え直すことでポジティブに解釈することができるのです。
2.ストレス解消法という観点でも同じことが述べられている
2.1.思考のアンバランスとはなにか
ネガティブ思考からポジティブ思考へという観点のほかに、ストレス解消という観点でも同じようなことが語られていたので紹介。本質的には両者は同じようなものなんでしょうけど。
鈴木祐氏の『超ストレス解消法 イライラが一瞬で消える100の科学的メソッド』は、書名や派手な表紙から受けるイメージとは異なり、多数の論文が引用されており、科学的に信頼のおける情報が詰まっています。
本書のなかで鈴木氏は、事実に基づかない思考、「思考のアンバランス」が激しいストレスを引き起こすことに言及しています。
(思考のアンバランスは)明確な裏づけもなしに物事を決めつけてかかり、そのせいで大きなストレスが発生する現象を指しています
鈴木祐(2018)『超ストレス解消法 イライラが一瞬で消える100の科学的メソッド』鉄人社(p.49)。
これは、ここまで説明してきた「人が事実に対して不相応な感情を抱く」という現象と同じことを言い表しているといえるでしょう。
2.2. 思考のアンバランスが治ると効果は絶大
この思考のアンバランスは、簡単には治せないものですが、治ったときの効果は大きく、ストレス解消に大きく寄与するといいます。
残念ながら、「思考のアンバランス」には特効薬がありません。これらの思考は、長年の習慣で身についた「脳の癖」のようなものです。(中略)やや長い道のりにはなりますが、それだけに成功した時の効果は絶大。
鈴木祐(2018)『超ストレス解消法 イライラが一瞬で消える100の科学的メソッド』鉄人社(p.51)。
本書では、本記事で紹介した「事実と感情」を切り分けると同じように、様々な思考のアンバランスを解消するための方法論が紹介されています。興味のある方はぜひ。即重版されたそうですが、納得の内容です。
3.事実と感情を切り離す練習の実践例
実践例として、ぼくが残業せずにぱっと帰るときの思考について考えてみましょうw
- 今日は仕事も終わったし、やりたいことがあるから、他の人は残っているけれど早く帰った。
- でも、他の人のフォローができたかもしれないし、最近早く帰ることが多いから、それを気にしている人がいるかもしれない。
- だから、早く帰っても申し訳ない気持ちやなんともいえない感情を抱いている(もしくは早く帰るのをやめる)。
残業の多い職場で働いているとわりによくある状況なのではないでしょうか。
これをぼくは下記のように考えるようにしています。
3.1.実践例
事実
- 今日は仕事は終わった。遅れも出ていない。
- 家でやりたいことがある。
- 他の人は残っているけど早く帰った。
思い込み
- 他の人のフォローができたかもしれない。
- 最近早く帰ることが多いから、それを気にしている人がいるかもしれない。
結果
- だから、早く帰っても申し訳ない気持ちやなんともいえない感情を抱いている。
- (もしくは)早く帰るのをやめて、次の日の仕事に手を付ける。
反論
- 他の人でフォローができそうな人は見る限りいなかった。本当に必要であれば声がかかるはずだ。
- 他の人も早く帰るときは帰る。それに誰かに何かを言われたわけじゃない。そもそもそんなに空気の悪い職場じゃない。
- 仕事も遅れてないし、早退ではなく、定時退社だし、申し訳ないと思う必要はない。
3.2. なんとなく感じていたモヤモヤは被害妄想だった
こんな具合で考えることで、なんとなく感じていたモヤモヤ(ネガティブな感情・ストレス)を低減することができるわけですね。
実際、ぼくが早く帰ることで何かを言われたことはまったくないので、ただの被害妄想なわけです。
それでも人間はそう考えてしまうだけでネガティブな感情を抱く。それを解消しようという思考方法です。
訓練を重ねていくなかで、鈴木氏のいう「脳の癖」が改善されていけば、そもそもネガティブなことを考えないようになっていくんでしょうね。
4.ネガティブ思考の人がポジティブ思考になるには「事実と感情」を切り分けて、無根拠な感情に反論しよう
ネガティブ思考からポジティブ思考になるには、まず無意識に抱いている思考に目を向けます。
そうすると、事実と感情が混ざっている状態になっていますから、それをきちんと切り分けてあげます。
そして、根拠のない感情に対して「そんなことはない」と反論していきます。
そうすることで、漠然としていただいていたネガティブな思考について「そんなことはないんじゃないか」と気づくことができるというわけですね。
ぼくも絶賛挑戦中というものではありますが、科学的にも信頼できるものという評価も多いですものなので、おすすめできます。
ストレスがないわけじゃあないですけど、なんだかんだ楽しく働いているので、効果はありそうですよw
※ここで説明した内容は医療行為とは異なるものです。深刻な症状を持っている方は専門家の治療を受けてください。
意外と知らないメイリオUI・Yu Gothic UI。UIフォントとはなんなのか

Windowsを使用していると、WordやExcelなどでフォントを選択する際に、「UI」と名前のついたものを見かけます。
- Meiryo UI
- Yu Gothic UI
- MS UI Gothic
不思議なことに「UI」という名前のついていない同じようなフォントも用意されている様子(なぜか日本語になる)。
- メイリオ
- 游ゴシック
- MS ゴシック
デザイナーの方であればそれぞれの違いを理解していたり、そもそもMacユーザーだったり、「そもそもそんなフォント使わない!」といったケースが多いのかと推測しています。
しかし、そうでない方たちは、なんとなく利用している方もいるでしょう。
ここではそうした方に向けて、UIフォントとは何かを説明し、非デザイナーのような方でもUIフォントを意識して利用できるケースがあるかを説明します。
UIフォントの概要
UIフォントと普通のフォントは幅が違う

上記の画像をみるとわかるように、同じ文字・文字数であるにも関わらず、表示幅が異なることがわかります。
メイリオとメイリオUIは同じようなデザインの文字ではありますが、文字の幅が異なるという違いがあります。他のUIフォントについても同じような特徴があります。
UIフォントが作られた理由はWindowsのUIのため
UIフォントはMicrosoftがWindowsで使用するフォントとしてつくられたという背景があります。 我々が普段Windowsを使っているとき、ファイル名やメニューに使われているのはUIフォントです。
下記のような画面を開いているときのフォントは、デフォルトでUIフォントが使われています。
「ドキュメント」とか「ミュージック」とかがそうですね(Windows10では、おそらくYu Gothic UIが使われている)。

なぜ幅が狭いのか
Windowsでメニューやファイル名などを表示するときには、限られたスペースのなかに文字を入れる必要があります。
英語であれば、文字の幅が狭いためスペースを取らないのですが、日本語だと、通常よりも幅をとってしまいます。
そのため、幅の狭いフォントを使用しているのだとか。
デザイン的な観点では評判悪い
MS御用達のUIフォントはデザインの観点からは評判が悪い印象。
文字の間隔というのは、デザイナーであれば、わざわざ数ピクセル単位で調節するような領域です。
それをUIフォントは「詰めるだけ詰める」なんてことをやってしまうわけですから、美しくないと感じる人がいるものうなずける話。
下記サイトでよい感じにボロクソに書いているのご参照ください笑
参考 いまさらながら見直したい——Windowsの和文フォント事情2016
Excelで使うのはおすすめ

とはいえ、UIフォントを使うとよい場面というのもあるかと。
例えば、ぼくの場合は、EXCELの資料を作成するときにUIフォントを使うことがあります。
上記の画像を見るとわかるように、UIフォントは幅が狭いため、限られたセルの中に文字を収めることができるんですね。
「これ以上セルの幅を広げると、表が画面に収まらなくなって不便」といったときにぜひ活用してみてください。
UIフォントは普通のものとどう違うのか、これを今回知っただけで、活かせる機会が生まれると思いますよ。
メイリオはまだ知っていたとしても、「游ゴシック?」となるかたは下記も。
フォントに限った話ではないですが、とりあえずデザインについて気になったら、下記がおすすめ。とても有名です。
知ると考え方が変わる。ポジティブ思考のメリットとデメリットはなにか。ネガティブ思考にもメリットはあるのか。

ポジティブ思考とネガティブ思考は物事を解釈するときの考え方、説明スタイルが異なります。
参考 ポジティブ思考の意味がわかる。3つの説明スタイルに基づくネガティブ思考との区別の方法
今回はそもそもポジティブ思考であることのメリット、デメリットについて説明しようかと。
ポジティブ思考は一般的に漠然と「良いこと」と思われていたり、その一般論に対する反動か「怪しい」「気持ち悪い」といった印象を持たれていたりします。
しかし、実はデメリットもあるんですね。
それから、一般に悪い印象を持たれているネガティブ思考にもメリットはあります。
ここでは双方の特徴的なメリットについて解説していきます。で、その裏返しのデメリットについても補足をするという形を取ります。
また、メリットとデメリットを踏まえたうえで、「じゃあどうすればいいのよ?」という点についても簡単に説明しようかと。
[:contents]
今回、引用するのは本書。著者はポジティブ心理学の権威で、ペンシルバニア大学のマーティン・セリグマン教授。
ポジティブ思考であることのメリットは「諦めないこと・続けられること」
メトロポリタン生命(書籍での表記のママ。メットライフ生命というほうが耳馴染みがある)で、保険外交員を対象にとある実験が行われました。
その結果、ポジティブな説明スタイルを持ち合わせている外交員のほうが、より多くの保険契約を成立させることがわかったとのこと。
これはポジティブな人のほうがトークがうまいということでなく、断られたときにそれをポジティブに解釈するということが起因すると考えられています。
※ここでは、ASQというのは、対象者の楽観度を図るテストであるという理解で十分でしょう。
ASQで上位半分の人たちは、下位半分の人たちよりも二〇パーセント多く保険契約を成立させた。上位四分の一は下位四分の一よりも五〇パーセント多く契約を取った。ここではキャリアプロフィールも同じような予測能力を示した。得点が上位半分の外交員は下位半分の外交員よりも三七パーセント多く契約を取った。二つのテストをあわせると(これらは別々の立場から受験者を見るので重複しない)、両方で上位半分に入っていた外交員は、両方で下位半分にいた外交員よりも五六パーセント多く契約を取った。
マーティン・セリグマン(1991)『オプティミストはなぜ成功するか』講談社(Kindleの位置No.1949-1954)
保険外交員は営業をかけても10回に9回は断られます。
断られるたびに「やり方が悪かった」「自分はダメだ」と考えてしまうと、すぐに会社を辞めてしまうでしょう(事実、本書によると保険外交員は一年で半分は辞めるそう)。
しかし、ポジティブ思考の人は、「忙しいときだったんだろう」「虫の居所が悪かったのだ」といった解釈を行うことで、長く仕事を続けることができると考えられます。
ここでいう「諦めない」とは、ネガティブ思考の人が精神的ダメージを負うような出来事を、ポジティブな解釈を行うことでそのダメージを低減できるから、物事を長く続けることができるという意です。
ネガティブ思考であることのメリットは「現実を直視できる」こと
ネガティブ思考を持っている人は現実を直視することができます。
詳しくは後述しますが、ポジティブ思考の人は自分に責任がある場合でも「他人だけが悪い」と考えたり、なにかを行うときに「どうにかなるだろう」と考える傾向があるんですね。そしてそれが実際と異なる場合もある。
これは説明スタイルについて知っていると、しっくりくる話だと思います。
これは実験によって簡単に試すことができる。口頭のテストを受けさせ、二〇回できて、二〇回間違えるように操作する。あとで結果はどうだったと思うかと尋ねる。すると、うつ状態の人は例えば二一回できて、一九回間違ったというふうにほぼ正確に答える。過去をゆがめて覚えているのはうつではない人々で、一二回間違えて二八回できたなどと答えるのである。
マーティン・セリグマン(1991)『オプティミストはなぜ成功するか』講談社(Kindleの位置No.2080-)
上記の実験では、どんな人でも10問正解、10問不正解になるテストを受けてもらい、それについて自己採点をしてもらいます。
すると、うつ状態の人はほぼ正確に自己採点できるのに対して、そうでない人は正解を多めに推測してしまうということです。
現実を直視できるとどんないいことがあるでしょうか?
例えば、経理だったり、プログラマーだったりという仕事は、失敗が許されない仕事です。「なんとかなるだろう」で進めていくと、大きな問題になることもあるでしょう。
投資の世界でも、損が出ているときに「いつかは利益が上がるだろう」という推測ではなく、現実の情報を見て投資先を変える必要があるでしょう。
企業の業績が傾いているのに、「景気が悪いだけ」というポジティブな説明をしていては、企業内部の問題を見落とすかもしれません。
悲観主義は、私たちがしばしば必要とする現実主義を支えているのではないだろうか? 人生には楽観主義では正しく対処できない場面がよくある。私たちは取りかえしのつかない失敗をすることがあるが、こういうときにバラ色のめがねで見るのはなぐさめにはなっても、現実を変える力はない。
マーティン・セリグマン(1991)『オプティミストはなぜ成功するか』講談社(Kindleの位置No.2040-2043)
ネガティブ思考は一般に「よくないよね」というイメージがあります。
しかし、一概にもそうとはいえず、ポジティブ思考よりも優れている部分もあるんですね。
ポジティブ思考とネガティブ思考のデメリット
ネガティブ思考の人は、物事をネガティブに解釈してしまうので、保険外交員のような仕事が長く続きません。
何度も勧誘を断られることでストレスを感じるのだとするなら、ネガティブ思考の人はポジティブ思考の人に比べてストレスを感じやすいということになります。
ポジティブ思考の人は、物事を事実とは異なる解釈をする傾向があります。
ポジティブ思考の人だろうと、ネガティブ思考の人だろうと、目の前で起こっている物事は同じです。
しかし、ポジティブ思考の人はその物事を楽観的に解釈します。それが現実とは異なった解釈になる危険性があるということですね。
なにか失敗をしたときに、自らの問題から目を背けて「漠然と次はうまくいだろう」「ぼくには才能がある」と考えても、問題が解決するとは思えません。
ぼくとしては、失敗の原因を分析するときは悲観的な目で冷静に原因を探り、次に挑戦するときは「この原因を解決すればうまくいく」「改善を続ければいつか成功できる」と楽観的な思考を用いるのがよいと考えています。
これは後述する「柔軟な楽観主義」であるとぼくは考えています。
結局、ポジティブとネガティブどっちがいいの?
じゃあポジティブ思考と、ネガティブ思考どっちがいいのよという話になります。
著者のマーティン・セリグマン教授は、『オプティミストはなぜ成功するか』のなかで、オプティミスト(楽観主義者)のほうが成功するということを語っています。
一方で、前述のようにネガティブ思考にもメリットがあると語っている。
そこで「柔軟な楽観主義」というものを提唱しています。
ポジティブ思考には大きな効用がある一方で、ネガティブ思考にも良い点はある。だから、状況に応じてポジティブ思考とネガティブ思考を使い分けていこうということです。
第 12 章以降の〝変身術〟の目標は、どんな状況にでもやみくもに楽観主義を適用しようというものではない。柔軟なオプティミストへの変身をはかろうというものだ。困ったことに出会ったとき、それをどう考えるか自分でコントロールする力をつけるのが目的なのだ。
マーティン・セリグマン(1991)『オプティミストはなぜ成功するか』講談社(Kindleの位置No.3527-)
自分の思考は無意識に選択されているものですが、意識すればコントロールすることが可能です。
本書ではポジティブ思考が遺伝ではなく、"教育"によってもたらされる可能性が高いことを示唆しています。
この記事や関わる記事を読んだ方たちも、ポジティブ思考とネガティブ思考が物事の解釈の違いによってもたらされること、双方にメリットとデメリットがあること、そして私たちの思考は自分の意志でコントロールできることがわかりました。
それだけで、柔軟な楽観主義の素質が芽生えるものと考えています。
では、ネガティブ思考の人は、どうやってポジティブ思考になるのか。それはまた別の機会に。
うまくいかない時のことを想定しておくと目標の達成率がぐっと高まる

目標達成の理論についてはいろいろ書いてきました。
いろいろな目標設定の方法論のなかで、目標自体の設定ではなく、目標と合わせて考えておくといいものがあるというものがあります。
いわゆる目標達成のための話とはちょっと毛色が違うですが、非常に面白いので説明していきます。
うまく行かなかった時のことを想定しておく
目標の達成率を高めるためには、うまくいかなかった時のことを想定しておくとよいそうです。
例えば、ジムに通うという目標を立てたとしても、「今週は残業が多かったから」と断念してしまう。
そこで「残業が多かった場合は、会社近くの宿泊可能なジムに通う」(ブラック臭いけど)というように事前に想定して、対応策を準備しておくわけです。
うまくいかない時のことを想定する具体的な実践方法
If-Thenで考える
うまくいかなかった時のことを考えるという方法をシンプルに実践する方法が「If-Then」という思考です。
事前に「もしも(If)○○になったとき(Then)は□□する」と考えておくわけです。
非常にシンプルですが、非常に効果があるとのこと。
ニューヨーク大学の心理学者、ピーター・ゴルヴィッツァーとヴェロニカ・ブランドスタッターの研究によれば、たとえば、目標を達成するための行動をいつ、どこで、どのように取るなど、ざっくりと計画しているだけで、学生たちが目標を実現できる確立が四〇%上がったという。
エリック・パーカー(2017)『残酷すぎる成功法則』飛鳥新社(p.160)
これは「うまくいかなかったときにこうする」という使い方だけでなく、目標の達成のために「水曜日のときはランニングをする」といったような使い方もします。
WOOP
ポジティブ心理学について研究している、こちらもニューヨーク大学のガブリエル・エッティンゲン教授が「WOOP」という目標達成のための方法論を提案しています。
WOOPは下記の頭文字をとったもの。
- W:願い(Wish)
- O:成果(Outcome)
- O:障害(Obstacle)
- P:計画(Plan)
これの「障害(Obstacle)」にあたる部分がうまくいかない時のことを想定しておく部分になります。
願いで自分の夢やなりたい姿をイメージし(願い)、その願いに関する望む成果を書く(成果)、そして目標を達成するにあたって障害になるものを列挙していきます。以上を踏まえて、最後には計画を立てると。
例えば、「ブログの記事を週に3つ書く」という成果に対する障害と障害に対する計画として、下記のようなものを考えました。
- 残業続きで睡眠不足だから、疲れで土日に活動できない→平日はお金払ってでも会社の近くに泊まればいい(やっぱりブラック臭い)
- 週に3つの記事を書こうにもネタがないよ→そうしたら記事を書く時間を削ってもいいから、新しい本を買って読もう
- 記事を書くモチベーションがない→書き上げなくてもいいから、記事を書く画面を開いてみる
原田メソッド
学校教育の場で大きな成果をあげた原田隆史氏の成功するための方法論に「原田メソッド」というものがあります。
原田メソッドでは、うまくいかなかった時のことの想定について、
- 心・メンタル
- 技・スキル
- 体・健康
- 生活
の4つの項目で考えるべきだと主張しています。
人間を分析する観点は、「心、技、体、生活、その他」の5項目に集約できるのです。スポーツで大事なことは、「心・技・体」と言われます。中でも一流選手ほど「心」を重視していることは前にも説明しました。さらに、一流選手と呼ばれる人ほど、節制し無駄のない生活を送っています。そして、それ以外の部分。「成功のプロ」は「心、技、体、生活、その他」にわたって質の高い生き方をしているわけです。
原田隆史(2005)『成功の教科書 熱血! 原田塾のすべて』小学館 (Kindleの位置No.834-838)
ちなみに上記のような少し古い原田氏の本ですと、「その他」という項目もあります。しかし、「その他」という分類は、コンサルタントの世界では思考停止を示すものです。
そもそも「その他」と言われて、他のものほど効果的な想定ができるとは思えません。
それに気づかれたのか、比較的新しい本(一流の達成力)を参照すると、今回紹介している4つになっております。なので、下記の引用とは異なりますが4つで十分かと。
これまでで一番具体的な方法論ですね。これを先程もあげた「ブログの記事を週に3つ書く」という目標で例をあげてみます。
- 心・メンタル:記事を書くモチベーションが出ない→書き上げなくてもいいからブログの画面を開く。また少しでもいいから書き進める。
- 技・スキル:記事のクオリティが低く、書き進めたり・公開することができない→記事をいくつも書きあげなければクオリティはあがらないということを意識し、まずは現状のまま作業を進める。
- 体・健康:仕事が忙しく睡眠不足で頭が働かない→睡眠の質をあげる方法を調べる。記事のネタにもできる。寝具を買うのも手。
- 生活:仕事が忙しく平日にアウトラインを書く時間がない→どうにか昼休みの時間を確保できないか考える。通勤・退勤の時間は使えるはずだから、スマホでも作業できる仕組みを整える。
ちなみにこの原田メソッドについて、いわゆる怪しい自己啓発ではなく、ちゃんとした科学的根拠がありそうだぞという記事を書いています。
参考 成功・目標達成の技術「原田メソッド」の科学的根拠について考えてみた
「原田メソッド」の全体像・概要を知りたいのであれば、下記がおすすめ。
「〇〇のせいで上手くいかない」という言い訳について先回りしておくのが目的
目標を決めたのに達成できなかった時に「○○だったから」と言い訳をしてしまうのが人間です。
だから、先回りをしてこういう問題が起こった時はこうすると決めておくことで、その言い訳を使えなくするというのが本質なのかなと考えている次第。
本当は「こういう問題が起きたらこうする」と書けるなら、その問題が起きた時にその対処をすればいいんでしょうけど、実際には思い浮かんでもやらない。だってめんどくさいから。
しかも、「問題が起きた」というのは、目標達成のための行動をしないための便利な言い訳にもできてしまうわけです。
それを未然に防ぐのが、事前にうまくいかない時のことを想定しておくことの意味なのかと推測しています。
目標達成のために考えることはたくさんあって大変なので、今回紹介したWOOPや原田メソッドを使ってみるといいでしょうね。すでに完成された方法論には、目標達成に必要な要素が多く含まれています。
「根拠(エビデンス)がある」という前提のもの目標達成やら、成功法則やら、いろいろと気になる方は下記がおすすめ。
成功・目標達成の技術「原田メソッド」の科学的根拠について考えてみた
原田隆史さんという方の提唱する教育の法則「原田メソッド」というものがあります。
とある中学校に赴任した原田さんは、独自の教育により学校の陸上部を全国レベルに押し上げるなど大きな成果をあげました。
その成果を生み出す方法は「再現性」のあるものとし、その方法を原田メソッドとして開発したのだとか。
いわゆる成功だったり、目標達成といったことを「目標達成は技術である」とし、一つのやり方を提唱しているものというわけです。
詳細は株式会社原田教育研究所のHPをごらんくださいませ。
ただ、こうしたいわゆる成功の方法は「うさんくさい」と思われてしまうのも事実。自己啓発の大半は「成功の方法」だとか「目標達成の方法」をうたっているわけですから。
また、原田メソッドについてもいわゆるLP(ランディングページ)があります。
アフィリエイトや怪しい情報商材でも用いられている手法なので、原田メソッドに対してネガティブなイメージを持つ人もいるでしょう(いいものもあるんですけどね。相対的少数ではありますが)。
そこで、原田メソッドの内容から「これは!」と思ったものを抜き出して、それについて科学的根拠を紹介していきたいと思います。
ぼくとしては原田メソッドは理論を実践するための具体的な方法がまとめられていて、良いものだと考えています。
このあと紹介する理論を背景に原田メソッドが作られているのかはわかりません。
しかし、原田メソッドの説明とは別の観点から、その効果を補足することで「やはり有用そうである」という判断の助けになるでしょう。
原田メソッドの有用性を示す科学的根拠
目的は信じないと達成できない
成功にリーチするためには「決める」ことが絶対に必要です。成功にリーチするには、まず「成功したい」ではなく、「成功する」と決めなければならないのです。
原田隆史『成功の教科書 熱血! 原田塾のすべて』小学館(Kindleの位置No.185-186)
「リーチ」」という言葉は原田メソッドのなかに出てくるもので、「ティーチング」「コーチング」などと同じニュアンスのものと考えればよいでしょう。
成功するためには「できると信じ続けなければ目標達成はできない」と書かれています。
これは、ナポレオン・ヒルの『思考は現実化する』でも主張されていることです。
『思考は現実化する』は読んだことがなくても「名前は聞いたことはある」というような名著(だと思う)。
その有名さゆえに「思い浮かべるだけで勝手に本当になるよ!」みたいな胡散臭い解釈をする人がいたりいなかったり。
本書は著者がアンドリュー・カーネギーの支援のもと、エジソンやガンジー、T型フォードで有名なヘンリー・フォードなど、名だたる歴史的な偉人へのインタビューの結果がまとめられた本です。
この世に出回っている多くの自己啓発本が『思考は現実化する』を言い換えているだけなんで言われたりもしますが、やはり原田メソッドでも同じようなことが主張されています。
逆に言えば、多くの人が「信じないと達成できない」については共感を覚えているということなんでしょう。
もっとも『思考は現実化する』のようなケース集が科学的であるかというと微妙なのですが、有名な書籍と意見が一致しているということで紹介してみました。
できると信じられる適度な難易度の目標を設定する
原田塾では目標の難易度を「目標のゾーン(幅)」から導き出します。「目標のゾーン」の上限にあたる〔最高の目標〕と下限の〔絶対達成できる目標〕を設定し、そのゾーンの中で適正な高さの〔今回の目標〕を決めるという手法です。
原田隆史『成功の教科書 熱血! 原田塾のすべて』小学館(Kindleの位置No.569-571)
原田メソッドでは目標の難易度を決めるときに、「最高の目標」と「絶対に達成できる目標」(あとは引用にはないが中間の目標も)を書き出したうえで、その書き出したものの間の難易度を設定するようにします。
「億万長者になる!」なんていって、ただの人がいきなり凄まじく難易度の高い目標を設定することがありますが、たいてい何もせずに挫折してしまいます。だって本人だってまさか本当にそうなるなんて信じられないでしょう。
「俺は海賊王になる!」なんていって順調に道を歩んでいる人もいますが、彼は本気で信じていますからね。
下記で詳しく触れていますが、目標はモチベーション向上に寄与するという目標設定理論というものがあります。
しかし、(これはぼくの考えですが)目標が高すぎると達成できると信じられないからモチベーションも上がらないわけです。
また、心理学者アトキンソンの提唱した「達成動機理論」でも、目標は必ずしも高ければ良いわけではないとしています。
これについては下記で詳しく触れています。
参考 目標設定の秘訣はできるかできないか微妙な難易度にすること
原田メソッドは「熱血!」なイメージもあるものの、過度に高い目標を設定させるということはなく、ちょうど良い難易度の目標設定を促しているところが、個人的にイケてるなと感じるわけです。
目的のみ道の間に細かく目標を設定していく
オリンピックの金メダリスト、偉人、成功者を徹底的に分析した結果、そうではないことが分かったのです。一直線に見える彼らの成功への道のりを虫メガネでのぞくように調べてみたら驚きました。〝肉眼では見えないくらい〟細かい階段を毎日着実にのぼり、小さな成功へのリーチを繰り返していたのです。 つまり、5パーセントの「成功のプロ」、大きな目標を達成できる人ほど、たくさんの小さな目標を設定し、期日までに確実に達成していたのです。
原田隆史『成功の教科書 熱血! 原田塾のすべて』小学館(Kindleの位置No.1017-1021)
原田メソッドでは、大きな目的に至るまでの道にたくさんの目標を設定しておくべきだと主張しています。
数ヶ月や数年に渡る目標のモチベーションを維持することは、一つの目標だけでは難しいでしょう。
一ヶ月ごと、一年ごとというように最終目標に向けて小さな目標を設定していくべきということです。
企業でも中長期的目標を設定したとしても、やはり一年毎の目標を設定します。
長期のプロジェクトでも定期的にマイルストーン(この仕事はこの時期までに終わっていないといけないという指標)を設定するでしょう。
これは仕事の中でもよく使われているので、それほど違和感を覚える人はいないのではないかと。
ペンシルベニア大学心理学教授のアンジェラ・ダックワース氏も書籍『やり抜く力』のなかで大きな目的(目標)の下に細かい目標をたくさん設定するべきだと述べています。
具体的な個々の目標を一つに束ねるもの、全ての目標を貫く目的が必要なのだ。
アンジェラ・ダックワース(2016)『やり抜く力』ダイヤモンド社(p.88)
目標と目的の違いや、具体的にどうやって目標を設定していくのかということについては、下記で詳しく述べているのでぜひご参照ください。
「世のため、人のため」という目標が必要である
夢や目標には「私・有形」のものと「社会、他者・無形」の2つがありますが、さらに達成力を高めるために、この2つの対となる概念が存在します。 それは「私・無形=自分自身の目に見えない夢や目標、そして目標を達成したときの感情や気持ち」と「社会、他者・有形=社会や他者に対する目に見える夢や目標」です。
原田隆史『成功の教科書 熱血! 原田塾のすべて』小学館(Kindleの位置No.433-436).
原田メソッドでは、「売上1億」といった目標も必要であるが、加えて「社会を良くする」といった無形で社会全体に対する貢献も目標として設定するべきだとしています。
上記の具合で「私・有形」「私・無形」「社会・有形」「社会・無形」というふうに4つの観点から目標を設定します。
この社会全体に対する貢献というのは、企業でもよく「経営理念」という形で表されることが多いです。
京セラを創業者の稲盛和夫氏やヤマト運輸の社長であった小倉昌男氏、パナソニックの創業者の松下幸之助氏など、名だたる日本の経営者は「世のため、人のため」というようなことを共通して言っています。
そして、先ほど紹介した書籍『やり抜く力』のなかでも「世のため、人のため」という思想が成功に寄与するという研究が紹介されています。
グラントの研究によって、組織のリーダーにしろ、従業員にしろ、100%自分のことだけ考えて行動する人よりも、自分ことも社会のためも考えて行動する人のほうが、長い目で見た場合に、成功する確立が高いことが明らかになっている。
アンジェラ・ダックワース(2016)『やり抜く力』ダイヤモンド社(p.218-219)
小倉昌男氏については、下記の記事でまさに「世のため、人のため」といった思想と行動に触れているのでぜひご参照ください。ちょっと前に色々ありましたが、やっぱヤマト運輸はよい会社だと思うわけです。
参考 クロネコヤマトの理念と規制との戦いの歴史。意見広告に関して
じゃあ原田メソッドを使えば絶対に成功できるの?
ここまで原田メソッドが科学的な見地から、どうやら有効そうだぞというお話をしてきました。
よくある質問・批判として、「じゃあ原田メソッドを使えば絶対に成功できるの?」と言われれば、それは「No」でしょう。
あらゆる成功法則に言えることですが、結局長い間継続して努力し続けることでしか成果をあげることはできません。
「これを使えばあっという間に成功できます」なんてものはありません。
原田メソッドでは毎日日誌を書くべきとしていますし、目標設定も定期的にそれなりのボリュームのあるシートを埋める必要があります。
さらにはルーティンチェック表といって、やると決めた習慣がちゃんとできているか確認する表を毎日チェックします。
もちろん、その習慣が身についてこそ成功するという考えです。
そりゃあそこまでやれば、毎日なんとなく過ごすよりも成果は出るでしょう。ただ、それをやり続けることは相当に困難です。
車輪の再発明はしない。確率されている方法論を用いる
成功するための方法論として一定の支持を集めているいるものを使ったほうが効率がいい。
また、そういったものには努力を続けやすいような仕掛けがどこかにある。
だから、原田メソッドに限らず「成功の方法」なんてものが出回っているわけです。
もっとも儲けるだけのために「簡単に成功できるよ」と誘惑してお金を巻き上げるようなビジネスをやっている人はきっとどこかにいて、その影響でこうした自己啓発的なものには怪しいというイメージがあるものと思います。
ただそのイメージに従って、一概に「成功するための方法を考える」といった自己啓発的なものを否定していても、それはそれで向上心のない人物だと。
「そんなことを考えるのはダサい」と開き直っているのをかっこよく見える人もいるでしょうけど、それではつまらないですからやっぱりよい方法を探してみたいわけです。
そこで今回は原田メソッドについて、目標に関する理論や心理学の研究などの観点から考えてみました。
実際のところどのように実践しているか
ぼくはGoogle Appsと呼ばれるGoogleのサービス(ExcelとかWordみたいなもの)を使って原田メソッドの目標管理シートや日誌などのツールを独自に作成しました(セミナーを受けるつもりはありません)。
そして、それにちょろっとプログラムを書き足したりして、毎日継続しやすいような仕組みをつくって実践してみています(退勤の電車でも簡単にスマホ作業ができるようになっています)。
まだ1週間ちょいしか続いていないので、例にもれず「続けられない人」であることを否定できないのですが、これから継続して続けてみようかなと考えています。
ポジティブ思考の意味がわかる。3つの説明スタイルに基づくネガティブ思考との区別の方法

「ポジティブであることはよいことだ」と一般に言われている。
しかし、ポジティブであることとは何であるか説明できる人は少ないのではないだろうか。
また、ポジティブをよく知らない人がその意味を曲解して「笑顔であること」「常に前向きな言葉を呟くこと」など極端な行為に走る。
そういった人を見ることで、ポジティブという言葉に対して違和感を覚える人もいるのではないか。
今回はポジティブ心理学の権威マーティン・セリグマン氏の『オプティミストはなぜ成功するか』をもとに、「ポジティブである」とはなにかを説明したい。
この手の本にありがちな不必要に派手な表現の引用や、飛躍した論理構成で読者を引きつけることはいっさいしない。
ポジティブ思考は3つの説明スタイルで表される
起こった物事をどのように受け取るかという説明スタイルによって、ポジティブ思考の人間とネガティブ思考の人間に分けることができる。
例えば、「仕事での失敗」という物事が起こった場合、下記のような受け取り方が考えられる。
- 永遠に改善できない。また失敗を繰り返してしまう。自分のせいだ(悲観的な説明スタイル)
- 今回の反省を活かせば次は上手くいく。今回は運も悪かった(楽観的な説明スタイル)
ポジティブであろうとネガティブであろうと、自分の周りに起こる出来事は変わらない。異なるのは起こった物事に対して、その人がどのような解釈をするのかということだけである。
そして、解釈を下記の3つの視点から分類することで、ポジティブかネガティブかどうかを判断することができる。
- 永続性
- 普遍性
- 個人度
ここでは悪いことが起こったときの反応をもとに3つの説明スタイルについて解説していく。
ポジティブであるとはどういう思考なのか
永続性(ネガティブ:永続的/ポジティブ:一時的)
悪いことを〝いつも〟とか〝決して〟という言葉で考えて、いつまでも続くと思っている人は永続的、悲観的な説明スタイルの人だ。〝ときどき〟とか〝最近〟という言葉で考えて、状況を限定し、悪いことは一過性の状態であると思っている人は楽観的説明スタイルの人だ。
マーティン・セリグマン『オプティミストはなぜ成功するか』パンローリング株式会社(Kindleの位置No.1003-1005)
- ネガティブ思考の場合:起こった悪い事が永遠に続くと考える(例:失敗してしまった。私はこれからも同じように失敗続きの人生を送ることになる)
- ポジティブ思考の場合:起こった悪い事が一時的なものであると考える(例:失敗してしまったが、次は上手くいく)
何かよくないことが起こったときに「もうダメだ」と考えてしまうことはないだろうか。これは説明スタイルが永続的であると考えられる。
ポジティブ思考を身につけたいのであれば、悪いことが起きたときにも「次は上手くいく、上手くやるための努力をする」といった一時的な説明スタイルで物事を解釈するべきである。
言うまでもないが、この説明スタイルを身につけることによって「最近良い出来事しか起こらなくなった」という魔法は起こらない。あくまで私たちのものの見方が変わっただけである。
普遍性(ネガティブ:普遍的/ポジティブ:特定)
オプティミストは悪い出来事には特定の原因があると考え、一方で良い出来事は自分のやることすべてに有利な影響を与えると信じる。ペシミストは悪い出来事には普遍的な原因があり、良い出来事は特定の原因で起きると考える。
同書(Kindleの位置No.1059-1061)
- ネガティブ思考の場合:起こった悪い事の原因は“全般”にあると考える(例:私がモテないのは容姿も性格もすべてイケていないからだ)
- ポジティブ思考の場合:起こった悪い事の原因に特定の物があると考える(例:私がモテないのは服装がダサいからだ)
なにか失敗したときに「どうせ私なんか」と考えるのは普遍的な説明スタイルの傾向がある。
逆に失敗をしたとしてもなにか特定の原因があるだけであり、自分自身のすべてが否定されるとは考えないのが「特定」の説明スタイルだ。
個人度(ネガティブ:内向的/ポジティブ:外向的)
悪いことが起こったとき、私たちは自分を責める(内向的)か、ほかの人や状況を責める(外向的)。失敗したときに自分を責める人は結果的に自分を低く評価することになる。
同書(Kindleの位置No.1094-1096)
- ネガティブ思考の場合:起こった悪いことは自分のせいだと考える(例:失敗したのは私のせいだ)
- ポジティブ思考の場合:起こった悪いことは外部要因のせいだと考える(例:失敗したのは景気が悪かった。失敗したのはあいつが悪い)
これをポジティブ思考だと言われて、「よいことなのか?」と違和感を覚える方もいるだろう。それについてはセリグマン氏も認識しているようで、本書でも触れている。
責任逃れを助長するようなやり方を提唱するのは私の本意ではない。なんでもかんでも内向的から外向的思考に変更することはないと思う。しかし、確実にこれをやるべき状況もある。それは、うつ病のときだ。
同書(Kindleの位置No.1134-1136)
また、企業の成績が悪いときに、企業自身の問題に目を向けずに「景気が悪いからで経営方針に問題はない」と考えることはポジティブであろうと正しいだろうか。
詳しくは言及しないが、ポジティブ思考はときに現実から目を背けることがある。
説明スタイルによって、ポジティブ思考であるかネガティブ思考であるかは分けることができる。しかし、世間一般で思われているように、ポジティブ思考であることがすべて正しい・良いということではない。
自分の失敗の原因を外部要因で考えてしまうことについては、下記でも詳しく書いています。
参考:成長できない人は失敗を「外部要因」のせいにする - ジブンライフ
正しく理解したうえでポジティブであろうとすることは良いこと
以上のように、ポジティブ思考とは3つの説明スタイルを用いる思考のことである。
とにかく笑顔であることやポジティブな言葉を呟くことには、一定の効果は認められることはあるだろうが、ポジティブ思考そのものを指してはいない。
また、単純にポジティブになると幸せがやってくるというような、非科学的な説明もある。しかし、説明スタイルを知れば、ポジティブ思考とは起きた物事についてポジティブに考えるだけで、起きている事象自体は変わらないことがわかる。
今回紹介した書籍で述べられているように、ポジティブ思考はあなたの人生に対してよい影響を与える。
本記事ではポジティブ思考とネガティブ思考の違いについて述べた。一方でポジティブ思考とネガティブ思考の特徴やどういった状況でどちらの思考を用いるかまで触れていない。
それについては別の機会で述べることとする。
今回はポジティブ思考とネガティブ思考がどう違うのかを知った。それをもとに「ポジティブというのは曖昧なものではない」「怪しさがあるものではない」ことを理解し、「ポジティブ」という言葉に対する違和感を拭い去ってもらえれば一番の目的が達成できたといえる。
楽観主義の恩恵は無限ではない。悲観主義は社会全般においても個人の生活においても役目を持っている。悲観的な見方が正しいときはそれに耐えなければならない。私たちはやみくもな楽観主義でなく、しっかりと目を見開いた柔軟な楽観主義を望んでいるのだ。
同書 (Kindle の位置No.4691-4694)
今回の内容をもっと簡単に解説しているのは下記の記事。
【就職活動】就職するなら上場企業がいいのか→「上場しているかどうかで選んではいけない」

過去の就職活動を振り返ると、わかりやすい指標として「上場企業」に就職したいという目標を掲げる学生は多くいました。
確かに、上場企業には「安定」「優良企業」「ホワイト企業」などといったイメージがあります。
また、学生であっても上場しているかどうかは、知識がなくても簡単に調べることができます。
そのため、学生は「上場」というわかりやすい看板にだけ注目して、企業の本質的な部分に関しては考えることをやめてしまう傾向があるのではないでしょうか?
そこで今回は主に下記のようなことについて書いてみようと思います。
- 上場企業という基準だけで会社を決めていはいけない
- 上場企業というステータスは一指標に留めておく
- 上場していない有名な企業は存在する
詳しくは後述しますが、「上場企業はダメだ」というような単純な話ではありません。
むしろ、おおざっぱにいえば「上場している企業のほうが経営成績や待遇面で優れていることのほうが多い」のは事実です。
それでもいくつか例外はあります。その例外を知らずに「上場企業がいい」と無思考なってしまうことが危険だということを主張していきます。
企業が上場する目的
企業が上場するのには理由があります。優良企業は必ず上場するというものではありません。
細かい説明は省きますが、基本的には資金調達という目的のために企業は上場します。
また、知名度の向上やブランド力・信頼性の獲得を期待するケースも多くあります。
下記の記事でも「上場の最大のメリットは億単位の資金調達」であり、同時に「知名度アップと優秀な人材の確保」をメリットに上げています。
上記のように、上場には理由があるのです。
逆に言えば、上場する必要がない企業もあるということです。また、そうした企業が必ずしも上場企業に劣るとは限りません。
上場のデメリット:利害関係者が増えて経営が難しくなる
上場にはいくつかデメリットもあります。その一つが利害関係者が増えることです。
企業は顧客、社員、取引先など多くの利害関係者に囲まれているからこそ、経営が複雑で難しいものになっています。
上場することでさらにその利害関係者が増えてしまい、経営が難しくなることが想定されます。
例えば、企業は社員に優位な経営を進めようとしても、株主の反対でそれが実現できないということもあるかもしれません。
パブリックカンパニーになれば多くの株主が現れ、多種多様な意見が上がってくることになります。上場する前は経営者の思いのままに進んでいた事業も株主の意向により変更を余儀なくされるケースも出てくるかもしれません。
もちろん上場には多くのメリットもあります。企業はメリットとデメリットを加味して上場するかどうかを判断しているのです。
単に「上場できるならする」というものではありません。
同じ業界でも上場している、上場していない企業
同じ業界で同じように有名な企業でも、上場している企業と上場していない企業があります。
「上場している会社が良い」のであれば、片方しかエントリーしないということになりますが、果たして自然な就職活動の戦略と言えるでしょうか。
ここでは非上場で有名な企業を紹介しています。
ビール・飲料業界など:サントリー
ビール・飲料業界でサントリーは非上場企業として知られています。
キリンやアサヒは志望するが、サントリーは志望しないというのは不自然ですし、企業としての魅力は同等でどこを第一志望とするかはその人次第でしょう。
サントリーは、清涼飲料を扱う子会社などの一部の子会社は上場しているものの、本体であるホールディングスは非上場。
建築業界:竹中工務店
竹中工務店も非上場企業として知られています。大企業でも非上場であるケースは、決して少なくはありません。
スーパーゼネコン5社(大林組、鹿島建設、清水建設、大成建設、竹中工務店)の一つであり、現在では5社の中で唯一、大阪市に本社を置く企業である(本店は大阪・東京それぞれに設置している)。
家電業界:ヨドバシカメラ
家電のヨドバシカメラも非上場企業です。少し古い記事ですが、下記では優れた収益体質の一因として非上場企業であることがあげられています。
非上場ゆえに他のお店よりも値切りにくという噂も……。
実はヨドバシは10年3月期以来、7~8%台の経常利益率を継続している。これは安値競争を繰り広げてきた家電量販大手の中で異彩を放つどころか、実に優れた経営実績を残してきた。ビジネスモデルの際だった強さを示してきたのがヨドバシカメラだ。
(中略)
ヨドバシの「我が道を行く」経営戦略の真骨頂はどこにあるのか。まず大きな要因として、非上場の同族企業である点が挙げられる。藤沢昭和・現社長が1960年に創業し、当初は「街のカメラ屋さん」だった。
上場企業でも待遇の悪い企業はある
下記2つの記事では、平均年収の低い上場企業と高い上場企業が掲載されています。
極端な例ではありますが、同じ上場企業でも年収300万円に届かない企業もあれば、年収2000万に届きそうな企業もあります。
参考①:上場企業版!「平均年収が高い」500社 | 賃金・生涯給料ランキング | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準
参考②:公開!平均年収が高くない500社ランキング | 賃金・生涯給料ランキング | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準
言うまでもなく、先ほど紹介したようなサントリーなどの非上場企業は、高水準の待遇を用意しているでしょう。
またぼくの勤めている企業も非上場ですが、少し前のデータでは平均年齢30台前半で年収960万円と公開していました。
このように、年収の面からいっても一概に非上場であるから年収が低いとはいえないことがわかります。
一方で、もちろん上場企業のトップクラスは目を見張るような待遇を用意しています。
しかし、上場企業と非上場企業で年収が明らかに差があるわけでない以上、「上場企業か非上場企業か」という括りで就職活動をすることはそれほど意味のあることではないのです。
一部上場かどうかは、一つの指標にとどめておく
「上場企業にしか興味はない」という考えが有用でないことを理解していただけましたでしょうか。
もちろん、繰り返しになりますが、基本的には上場している企業のほうが安定していて、待遇もよく、法律も守ると言われていますし、おそらくそれは正しいでしょう。
ただ、上場企業にも待遇の悪い例外はあるし、非上場にも待遇の良い会社があります。そして、それらは安易に無視できる割合ではありません。
そのため、上場しているかどうかはあくまで一つの指標に留めて、様々な要素を参照して志望する企業を決めて欲しい。
新入社員が最初に勝ち取るべき信頼は「ヤバイ!と言えるヤツ」

はやいもので、社会人になってからもうすぐ1年になります。
ということで、偉そうに仕事論などを語ってみることにしました。
どんな仕事であれ、研修が終わりに現場に配属されると、周りと先輩方との関係性を考えることになります。
そんなとき「早く信頼されるようになりたい、それなりの仕事を任されるようになりたい」と考えるはずです。
では、新卒でも現実的に勝ち取れる信頼とは具体的になんなのかを考えていきたいと思います。
アラートをちゃんとあげるヤツという信頼を得よう
新人が最初に得るべき信頼は、「やばかったらすぐに報告してくれる人間だ」というものだと考えます。
張り切っている新人は「仕事ができるやつ」だとか、「頭の切れるやつ」といった信頼を得ようとしますが、基本的に新人にはそんなことを期待しません。
ですから、仕事そのものの質の前に、いわゆる報連相ができる人間だという信頼を得るべきなのです。
しかし、報連相が大事とよく言うものの、具体的にどのような場面で使い、役立てるべきなのかは明言されることが少ない……。
「やばかったらすぐに報告」というのは、そんな具体的な使用例の一つだともいえます。
やばかったら報告できるやつが上司にとって「役立つ」理由
やばかったら報告できる部下は上司にとって非常に役に立つ。それゆえに信頼を得ることができるのです。
新人として現場に配属された直後は、誰かがその面倒を見る必要があります。
当然、仕事がわからなかったり、思うように進まなければ、上司がフォローすることになるでしょう。
もし部下が自分から問題があることを言わない場合、上司が常に部下の様子を観察したり、声をかけたりしなければいけません。
自分の仕事があるなかで、定期的に集中力を削がれることはそれなりの負担になります。
もし、部下のほうから「問題があります」と声をかけてくれるという確信があれば、上司は普段は自分の仕事に集中でき、声をかけられたときに対応すればよくなるのです。
問題があったら報告するというは意外と難しい
ここまで新人が信頼を得るために、問題があったら報告しましょうという話をしました。
「新人が最初に」ということで、あたかも簡単なような印象を受けますが、そうでもありません。
これは問題ないだろうということが大きな問題であり、後で発覚したり、わざわざ報告するべきか判断に迷う事象もあるでしょう。
これは経験の積み重ねによって身につけるのが基本的な方法だといえます。
人によって報告してほしいことが異なるということもありますが、それはその人と接することでしかわかりません。
ぼくの場合、最初は些細なことでもしつこくに報告し、その反応をみて報告の必要性を判断していました。こうすれば報告漏れは極力減らすことができます。
「細かい作業レベルの判断であれば、自分で判断し、最後に見てもらえればいい。お客さんになにかを伝達するときは報告必須」という具合に、判断基準が持てるようになります。
必要なときは上司の時間をもらって報告をし、必要ないものは自身で判断することで、上司と自分の効率的に時間を使えるようになるわけです。
ただ、ここで必要な報告を怠ると問題ですし、信頼も得られない。この塩梅が難しい。
新人らしい信頼の勝ち取り方を考えよう
ぼくが実際に仕事を覚えるなかで最初に意識していたことを紹介しました。
今回紹介した、問題をすぐに報告できるやつというのは新人が仕事で信頼を得る一つの事例です。
他にも方法はあるでしょう。
しかし、一般には新人という立場にあった方法を選択する必要があります。
張り切った新人が、自分の判断で仕事を進めてしまうことは、かえって信頼を損なうことにつながります(仮にうまくいったとしても)。
徐々に信頼を得て、少しずつ自分のできることの幅を広げていくことが好ましいでしょうね。
まあ、社風が独特だったり、俺は最初から注目されたいと考えていたりすると、色々やり方は変わってきますが、そういう人は自分で色々考えることになるんでしょうけど。
自分を過大評価せずに正しく自己評価をするための考え方

一般に人は自分を過大評価しがちである。
デビッド・シロタ(2006)の『熱狂する社員』では「仕事において、8割の社員が自分の働きは平均以上だと考えている」という。
心理学博士、MP人間科学研究所代表の榎本博明氏も「誰もが「自分は正当に評価されていない」と思う心理学的理由」のなかで、下記のような調査を紹介している。
心理学者ダニングたちの調査によると、リーダーシップ能力について70%の者が「自分は平均より上だ」とみなしており、「自分は平均以下だ」とみなす者はわずか2%しかいなかったという。平均というのは真ん中を意味するわけだから、70%の人が平均を上回るなどということは統計的にあり得ない。
つまり、人間は実際の能力が低いとしても、自分の能力は高いだろうと判断してしまう傾向がある。簡単に言ってしまえばナルシストなのである。
参考:能力が低い人は、自分の能力が低いことに気づく能力も低い
今回はこうした私たちの傾向を認識したうえで、自分を過大評価せずに、正しく自己評価するための考え方を紹介する。
この方法に科学的根拠はない。しかし、名言と経験をもとに考えだしたものであり、これに共感することができるのならば、自分をコントロールするツールとして役に立つはずだ。
落語の名言「下手だと思ったら、それは自分と同じくらい」
落語家 、古今亭志ん生のものとされる名言に下記のものがある。
他人の芸を見てあいつは下手だなと思ったら、そいつは自分と同じくらい。
同じくらいだなと思ったら、かなり上。
うまいなあと感じたら、とてつもなく先へ行っている。
自分より下だと思う人は自分と同じ、自分と同じだと思ったら自分より上、自分より上だと思ったらはるかに上。
自分を過大評価しがちな私たちが、日々意識するべき考え方が上記のようなものだろう。
この考え方を知っておくことで、常に相手と比較したときに謙虚になれるし、また適切な自己評価につながるはずだ。
しかし、この名言を納得感を持って受け入れるためにはひとつ気になる点があることに気づいただろうか。
それは自分より下の人はいないのかという点である。
自惚れるべきではないという意味で、自分より下の人を強く意識するべきではない。しかし、何であれ、現実的に自分より下の人が一人もいないというのは考えづらい。
自分より下の人を我々はどう思っているのか?
先程の名言に沿って考えるなら、私たちは自分より下の人をどのように認識しているだろうか?
答えは「認識していない」である。
その人が本当に自分よりも下の次元にいる人であるのなら、わざわざ意識していないはずだ。
例えば、自分よりもはるかに年下の子供に対して「私はこの子供と比べて優れている」などと考えるだろうか?
私たちは自分の周りの人すべてを意識しているわけではない。であるならば、「自分が意識している人の中に上の人も下の人もいる」と考えるよりも、意識の外に下の人がいると考えるほうが自然ではないだろうか。
意識している時点でライバル
だから「あいつは認めない、あいつは下手だ」と言っている時点で、自分に近いところにいる存在だと認識してしまっている。
悔しいけれど、意識してしまっている時点で彼らはライバルなのだ。
だから、他人と比較して「あいつには勝っている」と考えることは意味がない。
本当にその人を超えたときに起こる事象 というのは、努力しているうちに気づいたら、その人について忘れているというものだといえる。
まとめ「自分を過大評価せずに自己評価する方法」
本日の話を総括すると以下のようになる。
自分よりも上だと思う相手ははるかに上にいえる。自分と同じ程度だと思う相手は自分よりも上にいる。自分よりも下手だと思う相手は自分と同じくらいである。自分よりも下の相手のことを人は意識すらしない。
この記事では、自己評価に関する名言に「自分より下の人はどうなのか」という補足を加えたが、決して自分より下の人を認識したり、それを意識することを薦めるものではない。
あくまで、自己評価を高くしがちな自分を戒めるためにこの考え方を利用してほしい。
この考え方に基づけば、自分の認識している範囲にいる人は自分と同等かそれ以上ということになる。謙虚であれという一般的な教訓はやはり正しいのといえるだろう。
偏差値51の高校生でも受かった!基本情報技術者試験(FE)の勉強法
以前、文系・実務未経験でも受かった!応用情報技術者試験(AP)の勉強法 という記事を書きました。
この記事を読んでくださる方が意外に多くおり、需要があると感じました。そのため、昔の記憶を掘り起こして基本情報技術者試験の勉強法についても書いてみます。
前述の応用情報技術者試験の勉強法と多くは変わらないため、応用情報に挑戦するときにもこの勉強法での経験が活きてくると思います。
ぼくの合格状況と基本的なプロフィール
試験結果
- 午前問題:80点
- 午後問題:68点
ずいぶん昔に受験したため、受験結果の画面は残っていませんが、上記のような成績で合格しました。
当時、高校2年生だったことを踏まえると、なかなか頑張っていたんだなぁと思わされます。
合格当時のプロフィール
- 高校2年生(17歳)
- 情報系の学科(基礎の基礎は授業で学んでいる)
- 当時の高校の偏差値51(今見たら50を下回っていた)
商業高校の情報システム科に所属していました。情報が学びたくて、偏差値の一番”高い”商業高校に入学したものの、高くても偏差値51という具合でした。
資格の勉強が盛んで、基本情報の合格者もちらほら出ていましたし、年に1人は応用情報の合格者もいました。
基本的な勉強の進め方
まずは午前問題をきっちりと固める
基本情報には午前問題と午後問題があります。同時進行で勉強していくという方法が思いつきそうですが、効率的ではないでしょう。
午前問題が基礎的な問題が出題されます。午後問題は基礎的な知識が身についていることを前提として応用的な問題が出題されます。
ですから、基礎が身についていない段階で午後問題に手を出すべきではありません。
基本情報に登場する用語や概念をしっかりと理解してから次に進みましょう。
勉強方法は「とにかく問題を解きまくる」
勉強方法は「教科書を読んで理解する」のではなく、最初から問題を解きまくりましょう。
最初はわからない問題ばかりだと思いますが、問題を見たあとに解説を読んで理解するということを繰り返して、徐々に解ける問題を増やしていきます。
もちろん解説を読んでもわからないときに教科書を参照することは望ましいことです。
とにかく、教科書を読んで理解してから問題を解き始めようというアプローチはおすすめしません。
午前問題の勉強法
過去問を8割以上取れるまで、最低過去5回分はやる
午前問題は過去問を繰り返し解きます。午前問題では過去に出題された問題が、試験の多くを占めています(選択肢の順番も同じ)。
ですから、過去5~10回分の問題を解いて、すべて合格圏内に達するようになれば、実際の試験でも合格できる可能性が高いといえます。
上記の方法の勉強でおすすめなのが、基本情報技術者試験ドットコムの過去問道場です。
上記サイトは過去問を1問解くごとに正誤が出て、そのあとに解説が表示されます。
スマホでも利用可能なので、電車でも使えるのも便利です(基本情報の教科書の多くは分厚くて重いので)。
用語を覚えるだけでなく概念も覚えないと苦しい
前述しましたが、過去問を解いて、問題を暗記するだけではいけません。
用語の意味だけでなく、その概念や仕組みも理解するようにしましょう。
過去問とは違う形で出された問題や、応用的な理解を問う一部の問題に対応できなくなってしまいます。
特に計算問題では、同じ計算のパターンはあまり出題されないため、問題文を見て計算方法から考えられるようになる必要があります。
午後問題の勉強法
選択問題でどれを選ぶかがカギ
午後問題で最初に考えることは、「どの問題を選択するか」です。
午後問題最後の大問は、5つの問題の中から1つを選ぶ方式となっています。
ここでどの問題を選ぶか、またどのような戦略で試験に望むかが、合否を大きく分けます。
文系やプログラミング未経験の方は表計算を選ぶことが基本になります。しかし、数年前から表計算でもマクロ(簡単なプログラム)の問題が出されるようになったため油断はできません。
プログラミング経験がある方、実務経験がある方は得意な言語を選びましょう。
そして、大切なのが選択問題は1つに絞らず、予備を準備しておくこと。
例年、選択問題の難易度はバラバラで、「俺の選択問題だけ異様に難しかった」なんてことがあります。
そのため、選択問題は本命と予備の2つ程度準備しておくことが望ましいです。
午後問題は過去問題ではなく「予想問題」を重点的にやる
午前問題では過去問題を推奨していましたが、午後問題は「予想問題」をおすすめします。
午前問題と違い、午後問題は過去問題がそのまま出題されることがないからです。
ですから、午後問題の傾向を分析し、予想問題を多く収録している教科書を選び、勉強を進めていくべきでしょう。
過去問題を解くのは、ある程度慣れたあとに「こういう感じなのか」と傾向を理解する程度でよいでしょう。
なお、ぼく個人は下記の教科書を愛用していました。
そもそもの「努力」の考え方
最後にこのブロクでよく書いているような内容を。
アメリカの教育会でも支持されているGRIDという概念があります。その書籍『GRID』のなかで、成果を出すための正しい努力の方法として、「意図的な努力」が語られています。
成果のでない努力をする人は、やたらと勉強時間を割くことだけが成果を出すための手段だと思い込んでいることがあります。
しかし、基本情報でも同じように、ただ無思考に勉強するだけでは成果につながりません。
この記事で説明したような戦略を持って、「意図的な努力」を継続して行ってください。それが合格への近道だと考えます。
参考:努力しても報われない理由は才能ではなく「意図」がないから
まとめ:基本情報技術者試験の勉強法
- 午後問題より午前問題に手を付ける
- 教科書を読むより、問題をとにかく解く
- 午前問題は過去問題を解く
- 午後問題は過去問題ではなく、予想問題を解く
基本情報技術者試験の勉強のための方法論についてお話しました。
間違った方法で勉強を続けることは、時間の無駄です。この記事でなくとも自分にあった勉強法を見つけ、取り組んでみてください。
みなさんが基本情報に合格することを願っています。
【書評】『SINGLE TASK』はシングルタスクでの仕事術を教えてくれる本
『SINGLE TASK 一点集中術――「シングルタスクの原則」ですべての成果が最大になる』はマルチタスクを否定し、シングルタスクで仕事をすることを薦める本です。
「仕事の生産性をあげるには、いかに複数の仕事を効率的にこなすか」が注目されがちです。
しかし、本書はタイトルでもわかるようにマルチタスクを否定し、シングルタスクを推奨しています。その珍しさから、本書を手に取りました。
著者はデボラ・ザック氏。コーネル大学ジョンソンスクール(経営大学院)の客員教授を15年以上にわたって務めている人物でもあります。
本書は単に著者の個人的な仕事術が語られているだけではなく、神経科学の科学的根拠などをもとに論を展開しており、参考文献も明記されています。
ですから、ただの根拠のない自己啓発本ではなく、「科学的根拠に基づいている」「(妄信的に信じるべきではないが)学者の書いた本である」という点でも価値があるでしょう。
ただし、この本の本質的な話は前半で終わり。後半は相性がよいと感じれば読み続けるという具合でよいでしょう。
マルチタスクよりもシングルタスクで仕事をしよう
マルチタスクはそもそもできない
本書ではまず「そもそもマルチタスクは人間にはできない」と主張します。
人間の脳は2つ以上のことに集中することができません。だから、我々がマルチタスクだと思ってやっているそれは「タスクスイッチング」であるというのです。
しかし、多くの人が実感しているように、マルチタスクは効率が良い・頑張っている・要領が良いというイメージがあるのも事実。
このマルチタスクに関する肯定感を否定し、科学的根拠に基づいてシングルタスクを信じるようになれるかが、この本を読むうえでのポイントとなります。
スタンフォード大学の神経科学者エヤル・オフィル博士は「人間はじつのところマルチタスクなどしていない。タスク・スイッチング(タスクの切り替え)をしているだけだ。タスクからタスクへとすばやく切り替えているだけである」と説明している(p.40)。
シングルタスクのほうが効率がいい
次にマルチタスク(実際はタスクスイッチング)がいかに生産性を低下させるか、シングルタスクがいかに生産性を向上させるかについて主張していきます。
- タスクを切り替えるときに人間には一瞬の空白時間が生まれる。だからタスクの切り替えは少ない方がいい
- 優先順位をつけることができない複数の要求にさらされると、脳は圧倒され、うまく機能しなくなる(p.77)
これ関しては、マルチタスクはダメだという主張が特に説得的に書かれていた印象です。
下記記事で詳しく説明しているので、興味のある方はぜひ参照してみてください。
関連記事:マルチタスクができない根本的な理由。人間は「タスクスイッチング」しかできない。
どうやってシングルタスクを仕事に馴染ませるか
こうした仕事術の最大の問題、どうやって実践するかがこの本の多くを占めています。
例えば、シングルタスク実践するには、相手が話しかけてきたときに「ちょっと待って」と相手の行動を遮ることが必要です。こうした行動はどうしてもやりたくないと思ってしまいます。
しかし、何か作業をしながら相手の話を聴くことは本当に相手のためになるでしょうか。また、相手は自分だけに集中してくれているときと、メールをチェックしながら話をきいているとき、どちらのほうが「自分は尊重されている」と感じるでしょうか。
こうした点も加味して考えることで、実際に職場でも少しずつシングルタスクを導入できるようになっていくでしょう。
このような考え方が本書では多数紹介されています。本の後半は科学的根拠に基づいてというよりは、著者の仕事術の紹介という内容になります。
科学的に間違った仕事をしていないか
間違っていたら明確にわかるものと違い、「仕事の仕方」は間違っていてもなかなか気づくことができません。また、論理的に考えているようにみえて、実は頑張っている風に見せたい、嫌われたくないといった感情をもとに仕事の仕方が決まることも多くあるでしょう。
だからこそ、個人的な仕事術ではなく、科学的根拠のある主張を参考にすることは大きな意味があります。
そういった意味では、本書の前半部分にあるマルチタスクを否定し、シングルタスクを推奨するという部分は、特に読むべき文章だと言えるでしょう。
ただし、仕事の仕方はその人の仕事観・人生観に大きく影響しています。他者にこうした仕事の仕方を教えるときには、科学的根拠があったとしても相手の尊厳を傷つけないように配慮する必要があります。
(ワーク・ライフ・バランスの議論は特に仕事観・人生観の影響が大きいと働いていて感じることが多い)
『SINGLE TASK』の読むべきポイント
- マルチタスクという一般に良いと信じられている概念を否定し、シングルタスクを推奨しているところ
- 科学的根拠を持って「人間はマルチタスクができない」と主張している点
本書はそれほど分厚くもなく、内容も決して難しくないため、気軽に読める根拠のある自己啓発本だといえます。
仕事の仕方について考えていて、シングルタスクという言葉に惹かれる方は、ぜひ読んでみてください。
マルチタスクができない根本的な理由。人間は「タスクスイッチング」しかできない。

マルチタスクを「効率的に作業をこなす方法」として認識している人は多い。
しかし、実はマルチタスクを行うことは人間には不可能である。せいぜい私たちにできることは「タスクスイッチング」でしかない。
さらに、そのタスクスイッチングを行うと、むしろ生産性が低下してしまう。
つまり、私たちがマルチタスクをして生産性をあげようとしても、むしろ逆効果なのである。
私たちはなぜ「マルチタスクはできる」と勘違いしているのだろうか。また、タスクスイッチングとはどのようなもので、なぜ生産性が低くなるのだろうか。
- なぜマルチタスクは人間にはできないのか
- タスクスイッチングが生産性を下げる理由
- 【反論】マルチタスクはできる作業もあるのではないか
- 本日の根拠と参考文献
- 【まとめ】マルチタスクはできないし、タスクスイッチングは効率が悪い
なぜマルチタスクは人間にはできないのか
脳は2つ以上のことに集中することができない
私たちが想像しているマルチタスクとは下記のようなものだろう。
- 会議に出席しながら関係のない書類を作成する
- メールの文面を書きながら、気になる書類に目を通す

このように複数の作業を同時進行させることで、作業にかかる時間を省略することをマルチタスクという。
しかし、このような作業の進め方を人間は行うことができない。なぜなら、人間の脳は2つ以上のことに集中することができないからだ。
つまり、パソコンならともかく(コンピューターの脳であるCPUには4つくらいの脳が搭載されていることが多い)、人間の脳ではマルチタスクはできない。
では私たちがマルチタスクだと思っている"それ"はいったい何なのだろうか。
私たちの想像しているマルチタスクと”本当のマルチタスク”の違い
私たちがマルチタスクだと思っているものの正体はタスクスイッチングである。
先ほどの例で書くならば、以下のようになる。
- 会議に出席し話を聞く、一度聞くのをやめて、書類を作成する。名前を呼ばれたことに気づいてまた会議に参加する。
- メールの返信を書いているが、一度手を止めて書類に目を通す。キリのいいところまで読んだら、またメールを書く。
高い頻度で取り組むタスクを切り替えているだけで、作業の同時進行などできていないことがわかる。
マルチタスクが推奨されるのは作業を同時進行するからだ。しかし、人間の脳ではマルチタスクができず、実際はタスクスイッチングを行っている。
これを図にしてみるとわかるが、タスクスイッチングで生産性が向上するとは思えない。さらに不幸なことに、タスクスイッチングは人間の生産性を低下させる。

タスクスイッチングが生産性を下げる理由
タスクスイッチングが生産性を下げる理由は、タスクを切り替えるときのタイムラグにある。人間はタスクを切り替えるときに、認識できないレベルの空白の時間が生じさせる。
これを図にしてみると、タスクスイッチングを行えば行うほど、切り替えにかかる時間が生じ、生産性が低下することがわかる。

つまり、マルチタスク(実際はタスクスイッチング)はやらなければやらないほどよい。私たちはむしろシングルタスクを行い、生産性を向上させるべきであるとわかる。
【反論】マルチタスクはできる作業もあるのではないか
ここまでの内容を読んでいると、「いや、私は実際に作業を同時進行するようなマルチタスクを行っている」と思った方も多いだろう。
- 音楽を聴きながらドライブをする
- テレビを見ながら食事をする
実はこの反論は正しい。人間の脳は異なる脳の部位をつかう作業ならば同時進行することができるからだ。
だとしたら、仕事でもマルチタスクは通用するといえるだろうか?
残念ながら仕事でマルチタスクを行える機会は少ない。仕事で、異なる脳の部位を使うことは多くないと想定されるからだ。
会議の内容はテレビのように聞き流せるものだろうか? 内容を論理的に解釈し、それに対応した発言をしなければならないはずである。そのときに、論理的な主張の書類を書くことができるとは思えない。
私生活ならばともかく、仕事で与えられるタスクは性質の近いものが多く、同時進行させることは困難だろう。
もっとも、なにかをしながらドライブをすると、注意散漫になり、事故を起こしやすくなることは想像に難くない。
本日の根拠と参考文献
【参考文献】『SINGLE TASK 一点集中術 ―「シングルタスクの原則」ですべての成果が最大になる』
本書はマルチタスクは幻想であると否定し、シングルタスクを推奨する書籍である。
また、シングルタスクを実践するための手法にもページを多く割いている。マルチタスクを行わないのは失礼ではないのかといった主張にも反論が用意されている点が興味深い。
マルチタスク信仰は根深いが、少しでもシングルタスクに興味を持ったのであれば、是非読んでいただきたい。
デボラ・ザック著 栗木さつき訳(2017)『SINGLE TASK 一点集中術 ―「シングルタスクの原則」ですべての成果が最大になる』ダイヤモンド社
①脳は2つ以上のこと集中することができない
スタンフォード大学の神経科学者エヤル・オフィル博士は「人間はじつのところマルチタスクなどしていない。タスク・スイッチング(タスクの切り替え)をしているだけだ。タスクからタスクへとすばやく切り替えているだけである」と説明している(p.40)。
②タスクスイッチングには空白の時間がかかる
本書のなかで、マサチューセッツ工科大学のアール・ミラー博士が<人はなにかしているときに、べつのタスクに集中することはできない。なぜなら2つのタスクのあいだで『干渉が生じるからだ』>と述べていることに言及している。
そして、これがタスクスイッチングにかかる空白の時間だと主張している。
一般に一般に「マルチタスク」と考えられている行為は「タスク・スイッチング」にすぎない。(中略)タスクの切り替えには0.1秒もかからないため、当人はその遅れに気づかない(p.41)。
③脳の同じ部位を使わない作業は同時進行可能である
一般に一般に「マルチタスク」と考えられている行為は「タスク・スイッチング」にすぎない。(中略)タスクの切り替えには0.1秒もかからないため、当人はその遅れに気づかない(p.41-42)。
本書では同時進行可能なものについてはマルチタスクだと定義していないが、本記事では割愛している。
【まとめ】マルチタスクはできないし、タスクスイッチングは効率が悪い
- 人間は2つ以上のことを同時にできない→マルチタスクはできない
- 私たちがマルチタスクだと思っているものはタスクスイッチングである
- タスクスイッチングは切り替えに時間がかかるため、むしろ作業効率が下がる
- いわゆるマルチタスクよりもシングルタスクのほうが生産性向上に効果がある
「人と同じがいい人」と「人と異なるほうがいい人」がいる理由。それは人類の維持と発展のためである。

下記のような質問をいただきました。
人と違うことを恐れる人と好む人の違いとはなにか”という記事を読ませていただきました。
その中の、”世の中を動かすのが「人と違うことを恐れる人」で、世の中を変えるのが「人と違うことを好む人」”というフレーズが、感覚的には分かるのですが、自分なりの論理的解釈を出来ず、もう3日もこのフレーズのことばかり考えています。
そこで、お忙しいこととは存じますが、このフレーズについてもう少しヒント、解説を頂けないでしょうか。
参考記事:人と違うことを恐れる人と好む人の違いとはなにか - ジブンライフ
今回はこのフレーズについてヒントを書いてみようという意図で、人と違うことを恐れる人、人と違うことを好む人がなぜ存在するかについて説明していきます。
質問をいただいた記事では、個人の感性を中心にお話ししていました。
この記事ではもう少しエビデンスを加えて説明していきたいと思います。
また、今回は「人と同じがいい人」「人と異なるほうがいい人」という言葉を用いていきます。
- 参考にする書籍『内向型の生き方戦略』
- 「人と同じがいい人」と「人と異なるほうがいい人」がいる理由
- 実は「アリの社会」でも社会維持型と境地開拓型がいる?
- 余談:シン・ゴジラでみる境地開拓型と社会維持型のイメージ
参考にする書籍『内向型の生き方戦略』
今回の論理の多くは『内向型の生き方戦略―「社会から出て、境地を開拓する」という生き方提案』をもとにしています。
この書籍は外向型/内向型という人の性格の違いのようなものをテーマに扱っています。
一見すると、「人と同じがいい人」「人と異なるほうがいい人」というテーマとは関連がないように思うでしょう。
しかし、本書では外向型を社会維持型、内向型を境地開拓型に再定義しています。
これから詳しく説明していきますが、今回の話では、社会維持型は「人と同じがいい人」、境地開拓型は「人と異なるほうがいい人」になります。
「人と同じがいい人」と「人と異なるほうがいい人」がいる理由

内向型と外向型とはなにか
本題に入る前に、簡単に内向型と外向型について知っておく必要があります。
内向型/外向型という分類を提唱したのは、分析倫理学の祖である心理学者カール・ユングです。
そこからいくらか意味が変わってきているかもしれませんが、「内向的な性格」と「外交的な性格」という分類が人間の個性の一つとして成立しています。
内向的、外交的という要素は、人に応じてキレイに分けられるものではく、内向的な要素が多い人や両方の性質を持ち合わせているような人もいるとか。
また、これらの性質は生まれ持ったものであり、変えることができないと『内向型の生き方戦略』では述べられています。
内向型と外向型のどちらが優れているのか
下記でも触れられているように、「人付き合いが苦手」というイメージの内向的な性格は、劣っていると思われることがあります。
これは私の実感ですが、社会では「外向的な性格の人ほどよい」、「内向的な性格はあまりよくない」という雰囲気があるように思います*1。
しかし、外交的な性格が明らかに優れているのであれば、内向型の人間はすでに淘汰されているはずであると、著者は主張しています。
もし一方的に外向的な性格の方が優れているのであれば、五〇〇万年という人類の進化の過程で、内向的な性格は淘汰されているのが自然です*2。
そして、内向型と外向型の間に優劣はなく、ただ役割の違いのみがあるのだと論理を展開していきます。
社会維持型(外向型)と境地開拓型(内向型)の役割
冒頭でも説明したように、『内向型の生き方戦略』では、外向型を社会維持型、内向型を境地開拓型に分類しています。
そして、それぞれの役割を以下のように定義しています。
人類が生き残っていくためには、今過ごしている社会を維持していく必要があります。
一方で、人類が有事の際に生き残っていくために新しい技術を見つける必要もあります。
これらの役割を社会維持型・境地開拓型の人がそれぞれ担っているというのが、本書の考え方です。
結論:「人と同じがいい人」と「人と異なるほうがいい人」がいる理由は人類の維持と発展のためである。
本記事の本題である「人が同じでいい人」と「人と異なるほうがいい人」がいる理由は、人類の維持と発展のためであると結論づけることができます。
なんだか壮大な話しのように聞こえますが、人類という生命が維持、発展していくために、大まかに2種類のタイプの人間を用意したということですね。
人類の大半を占める社会維持型は(本書では8割としている)で、すでにできあがっている仕組みを円滑に動かしていく役割を担っていいます。
質問をいただいた記事の表現を用いるならば、世の中を動かすのが「人と違うことを恐れる人」が該当します。
そして、境地開拓型は今の人類の仕組みを変えたり、有事の際に対応できるようななにかをつくったりする役割を担います。
こちらが世の中を変えるのが「人と違うことを好む人」に当たりますね。
数年前に書いた記事ながら、『内向型の生き方戦略』と同じ方向を向いているようで、嬉しくなります笑
実は「アリの社会」でも社会維持型と境地開拓型がいる?
ここまでお話ししてきた内容は、説得的に書かれているものの、著者の推論である部分が多くあります。例えば、「境地開拓型はいざというときのために人と違う行動をとる」「内向型と外向型の割合は2:8である」などは科学的な根拠は今のところありません。
しかし、アリの社会では上記のことが科学的に証明されているのです。
北海道大学大学院研究員准教授の長谷川英祐氏の書籍『働かないアリに意義がある』をもとに簡単に説明していきましょう。
働きアリは当然働き者だと思われていますが、実は「まったく働かない働きアリ」が2割ほどいるといいます。
私たちが、シワクシケアリというアリで行った最近の研究では、1ヵ月以上観察を続けてみても、だいたい2割くらいは「働いている」と見なせる行動をほとんどしない働きアリであることが確認されました*5。
この現象は、複数のアリの巣の「働くものだけを取り出してもやはり一部は働かなくなる*6」といいます。
そして、この「働かないものを常に含む非効率的なシステムでこそ、長期的な存続が可能になり、長い時間を通してみたらそういうシステムが選ばれていた*7」と長谷川氏は述べています。
以上のことから、アリの社会の発展と維持のために、働かない働きアリがいるということがわかりますね。
一見すると、「働かないアリ」と「人と異なるほうがいい人」を同一視するべきでないように思えるかもしれません。
しかし、人と異なるほうがいい人は、みんなが同じ方向を向いて作業をしているときに関係のないことをしていたりなど、協調性がないことによる不快感も含め「あいつはちゃんと働いていない」と評価されることがしばしばあるでしょう。
そう考えると働かないアリと、境地開拓型の人々を同一視することがふさわしいと考えられるようになります。
人類においては完璧な科学的根拠のない今回の議論ですが、アリの社会では多くの興味深い事実が研究で発見されているという補足でした。
余談:シン・ゴジラでみる境地開拓型と社会維持型のイメージ
余談ですが、映画『シン・ゴジラ』に登場する「巨大不明生物特設災害対策本部(巨災対)」のメンバー達はまさに内向型、境地開拓型、人と異なるほうがいい人の集まりとして描かれています。
津田寛治氏が演じる森文哉は、巨災対について説明するとき「そもそも出世に無縁な霞ヶ関のはぐれ者、一匹狼、変わり者、オタク、問題児、鼻つまみ者、厄介者、学会の異端児、そういった人間の集まりだ。気にせず好きにやってくれ*8。」と述べています。
上記の表現から、巨災対は人と異なるほうがいい人の集まりであり、人類の非常時に活躍する一集団であると表現されていることがわかりますね。
一方で、外向型、社会維持型の人たちもゴジラの驚異に何らかの形で対抗していくわけですが、その関わり方は境地開拓型の人とは異なります(総理大臣、各大臣はまさに社会維持型的な人物ではないでしょうか)。
そうした点に注目して物語を楽しんでみても面白いかもしれません。
こうした映画でも、変人が世界を救うというアイデアが受け入れられていることを見ると、この記事で述べてきたことは、多くの人が感覚的には認識しているいことなのかもしれません。
*1:中村あやえもん(2017)『内向型の生き方戦略―「社会から出て、境地を開拓する」という生き方提案(Kindleの位置No.18-19) AyaemoResearchInstitute.Kindle版.
*2:同上 (Kindleの位置No.28-29)
*3:同上 (Kindleの位置No.53)
*4: 同上(Kindleの位置No.55)
*5:長谷川英祐(2016)『働かないアリに意義がある』Kindle版 中経の文庫 (Kindleの位置No.250-252)
*6:長谷川英祐(2016)『働かないアリに意義がある』Kindle版 中経の文庫 (Kindleの位置No.619)
*7:長谷川英祐(2016)『働かないアリに意義がある』Kindle版 中経の文庫 (Kindleの位置No.759-760)
文系・実務未経験でも受かった!応用情報技術者試験(AP)の勉強法
この記事では応用情報技術者試験の勉強法について考察しています。
平成29年度春の試験に合格し、本日、秋の試験が終わりました。
考えもまとまってきたし、キリがいいかなということで。
このあと詳しく説明しますが、ぼくは「文系でありながら、わずかな情報系の経験・商学・経営系の分野が得意・実務未経験(今は経験済み)」というちょっと変わったバックグラウンドがあります。
そういった点から、他の人には書けないようなアドバイスが書けたらと思います。
結論を端的にまとめると、「教科書を読む作業はそこそこにして、午前問題の過去問を解きまくり、基本的な用語・概念を理解したうえで、最後に午後問題をやる」というものになります。
ぼくの合格状況と基本的なプロフィール
試験結果
午前・午後問題も8割を超えました。
午後問題の選択では、技術的要素が比較的薄い、文系が得意とすると思われる分野を選択しました。

ぼくの基本的なプロフィール
大学では商学部で経営を専攻していました。
そのため、午後問題の経営・マネジメント系の分野は得意分野です。
また、文系といいつつも、高校時代は商業高校の情報系の学科で勉強しています。
そのため情報に関わる最低限の知識はありますし、プログラミングも「一応触ったことはある」というレベルです(言語COBOLが主ですが……)。
商業高校出身と言うこともあり、日商簿記2級を取得しています。
応用情報では会計の知識を問う問題がある程度出題される(午後問題の経営戦略など)ため、会計が得意がどうかで攻略の幅が広がります。
高校時代に基本情報技術者試験に合格しています。
しかし、5年以上前のことで、あまりその経験を活かすことはできませんでした。
基本的な戦略と勉強法
午前問題と午後問題の勉強の比率は午前が8割
応用情報技術者試験に合格した先輩からいただいたアドバイスとして、「午前問題を重点的に勉強し、午後問題は最後の仕上げの時期にやる」というものがありました。
そのアドバイスに従い、勉強時間の8割程度は午前問題対策に当てました。
そして、試験の2週間前から午後問題の対策を行いました。
この比率がぼくには非常にハマり、「午後問題解いたことないけど、それなりに解けるぞ!」という状態に。
午前問題の勉強で基本的な用語・概念を押さえたうえで午後問題に望むほうが、はるかに効率的であるということです。
勉強方法は「とにかく問題を解く」
資格の勉強方法は大きくに2つに分けられます。
- 教科書を読んで理解して、問題を解く(もちろんわからなかったら調べる)
- 問題を解いて、わからなかったら調べる
いろいろな資格勉強をしてきましたが、基本的に後者の戦略が間違いないです。
教科書を読むだけで覚えられる系の人や授業でその分野を教わる人などは前者の方法も用いてもいいかもしれません。
しかし、一般人が膨大な範囲の応用情報の内容を普通に教科書を読んで理解しただけで、点数がとれるようにはならないでしょう。
また、応用情報は過去問からの出題が多くありますから、過去問を勉強することは得点をあげるうえで大きな力になります。
そのため、教科書を読んでから問題に取り組むのではなく、最初から問題を解きながらわからない箇所を調べていくという勉強法をおすすめします。
もちろん、最初はすべての問題がわからないでしょうから、実質教科書を読んでいるようなものです。
しかし、それでも過去問に触れながら勉強を進めていくことには大きな意味があると考えます。
午前問題の勉強法
とにかく過去問を8割以上とれるまでやる
全体の8割を占めた午前問題の勉強方法は簡単です。
「応用情報技術者試験ドットコム」の過去問題を過去10回分解き続け、それぞれが8割以上とれるようになるまで繰り返し続けます。
応用情報技術者試験ドットコムはパソコン上で簡単に過去問に取り組むことができ、得点の集計や問題の解説もしてくれます。
スマートフォンでも気軽に使うことができるため、電車のなかなどのスキマ時間にもこれを利用するとよいでしょう。
問題を間違えたり、理解していない部分があれば、サイトの解説や教科書を読んでその分野を勉強していきます。
ちなみに利用した教科書は下記になります。
定番という扱いの本ではない気がしますが、低価格で全体を網羅している教科書で、特に使用していて不足は感じませんでした。
分厚い本ですが、PDFを無料で入手することができるのも魅力です。
とはいえ、この教科書を絶対におすすめするわけではありません。
それぞれにあったものを選ぶとよいでしょう。
最初がとにかくしんどい
この勉強法はとにかく最初がしんどいように思います。
なにも知らない状態で問題をとりあえず解いて、間違えて、よくわからない分野を問題が解ける程度にだけ理解する。
最初はできるようになっている気がしないですし、地道な作業が苦しく感じるでしょう。
しかし、知識が増えて行くにつれて、得点をとれるようになり、知識の点と点が結ばれていく感覚が得られるようになると、一気に調子があがります。
午前問題を理解した後に、午後問題を解いたときの「ぼくでも解けるのか!」という爽快感はなかなかのものです。
ぼくは過去10回分を2~3回解いたあたりで、コンスタントに8割を超えるようになってきました。
1回分で60分から90分かかりますから、それなりの時間をかけてきたように思います。
ちなみに、過去問を過去10回分やるといいましたが、個人の能力や出題傾向に応じて回数は変えていいでしょう。
ぼくは性格的な面から、過去10回分を8割越えを達成することで、安心して試験に臨むことができました。
午後問題の勉強法
午前問題に出るような「用語」や「概念」を理解してから勉強する
前述したように、午前問題を8割以上とれる程度の知識を身につけてから午後問題に取り組むといいでしょう。
午後問題は応用的な知識を問う問題ですから、問題のなかで情報に関する用語がたくさん登場します。
そもそもそれを理解できなければ、時間内に問題を解き、合格することは困難です。
ですから、用語・概念そのものの理解を問う午前問題を先に攻略することが大切になります。
午前をやりつつ、つい午後問題にも手を出してしまうのは、あまりよくないパターンかなと。
もちろん、心配であれば、問題を一通り眺めてみることはよいことでしょう。
使用した教科書は技術評論社の「試験によくでる問題集」
午後問題の勉強で使用した教科書は下記になります。
こちらは比較的定番として扱われることが多い印象ですね。
過去問題よりも、過去問題の傾向を分析してつくられた練習問題を重点的に解きました。
午後問題は過去問が出題されることがないため、午前問題ほど過去問の重要性は高くないと判断しました。
終盤に過去問を一度解いて「こんな感じの問題が出るんだな」という感覚を得る程度でよいと考えます。
この教科書では、午後問題の傾向分析がよく書かれており、まずはそれをじっくりと読むことが効率のよい勉強につながるでしょう。
記述問題を恐れる必要はない
応用情報に合格した先輩から「午後問題は国語の問題だ」というアドバイスをもらいました。
基本情報と応用情報の違いとして記述問題の有無がよくあげられますが、恐れることはないと考えています。
記述式とはいうものの、論文などと異なり、自分の考えや論理的な思考をそれほど求められるものではありません。
基本的には問題のなかから解答にあたる文章を抜き出して、要約して解答に書くだけのものが多いです。
文章を読んで、その意味・論理展開を理解できる程度の読解力があれば、簡単な問題は解くことができると感じました。
勉強をする際には、情報に関する知識以上に、問題文の理解ができているかが求められると考えることをおすすめします。
それから、本番ではわからなくてもとにかく埋めることも大切です。
記述問題の採点基準はそれほど厳密ではないという印象ですから、とにかく書いて、加点がもらえるよう努力するべきでしょう。
選択問題はどれを選ぶべきか
午後問題はセキュリティの問題以外は選択になります。
ぼくは技術的な知識よりもマネジメントの知識を問う問題ばかりを選びました。
「文系は応用情報のほうが受かりやすい」という人もいるくらい、応用情報は文系的な知識でも十分に通用するのです。
そのような選択をした理由は以下になります。
- 【弱み】情報系の知識は高校レベルである
- 【弱み】実務経験がない
- 【強み】経営・マネジメント系が得意分野である
- 【強み】日商簿記2級を持っており、会計の知識がある
「この問題を選ぶべき」というセオリーはないと考えます。
そのため、自分の性質に応じて問題を選ぶとよいでしょう。
情報の知識がある人であれば、なにかしら得意分野があるでしょうし、文系で情報の知識がなにもないということであれば、ぼくのような文系向けの問題が候補になるはずです。
とはいえ、午後問題は4問を選択することになりますが、5~6問は解けるようにしておくとよいでしょう。
得意分野であっても、その年によって妙に難しかったりすることがあります。
そのときに別の分野に逃げられるようにしておくことは欠かせないように思えます。
先ほど紹介した書籍にも「どの問題を選択するべきか」というアドバイスあるので、非常に参考になります。
応用情報技術者試験の勉強法以前の考え方
応用情報技術者試験「も」コツコツ継続できるかがカギ
わかりきった話ですが、結局のところ資格試験はコツコツと勉強を継続できるかで決まります。
努力せずに簡単に合格できる裏技など存在しません。
授業などで強制的にモチベーションを維持してくれる環境があるならともかく、学生や社会人はモチベーションの維持がカギになります。
誰に言われなくても物事を積み重ねていく習慣のある人は有利ですが、それができないぼくのような大半の人間はいかに継続するかが一番難しい(このブログでは主にそういうことを語ってばかりいます)。
スマホでスキマ時間を利用したり、分厚い教科書を持ちあるいたりなど、手の届くところに勉強の機会を設け、努力しやすい環境をつくることをおすすめします。
参考記事:努力しても報われない理由は才能ではなく「意図」がないから
参考記事:目標設定の秘訣はできるかできないか微妙な難易度にすること
なぜ当日に試験を受けに行かなくなってしまうのか
資格試験は申し込んだけれども、当日受けに行かないという人が多い。
なぜか。
それは、受験しようと思えるほど勉強をしていないからだと考えます。
応用情報「起床」試験なんてネタとして扱われることもありますが、まずは「受験しないともったいないと思える程度には勉強すること」が最も大切なことだと言えるでしょう。
まとめ:応用情報技術者試験の勉強法
- 教科書を読むよりも過去問や練習問題を実践形式で解いていく
- 午前問題の勉強に時間の多くを割く
- 午前問題の勉強は最初がとにかくしんどい
- 午後問題の勉強は午前問題で8割をとれるようになってから
- 午後問題は国語の試験。記述問題特別を恐れる必要はない
- 選択問題はバッファを1問は持っておくこと
ぼくが応用情報技術者試験に合格するために行ったこと、考えたことをまとめてきました。
この方法はスキマ時間を活用できるとはいえ、それなりに時間割く必要があると思います。
ぼくが応用情報技術者試験を受けたのは入社して2週間という、社会人といっていいのか微妙な時期です。
だからこそ、時間を割くことができたという面もあります。
そのため、仕事が忙しい社会人の場合は、また違った方法を模索しなければいけない部分があるかもしれません。
また「実務経験があるのは大きい」と、ある程度の経験を積んで感じます。
プログラミングやデータベースなどの最初の辛い時期を比較的に容易に乗り切れるというメリットがあるからです。
応用情報技術者試験ドットコムを活用することは大いに推奨されます。
会員登録をして、達成状況を確認することでモチベーションを保ち、電車の中などでで少しずつ問題を解いていくとよいでしょう。
この記事を読んだ方が応用情報技術者試験に合格することを願っています。















